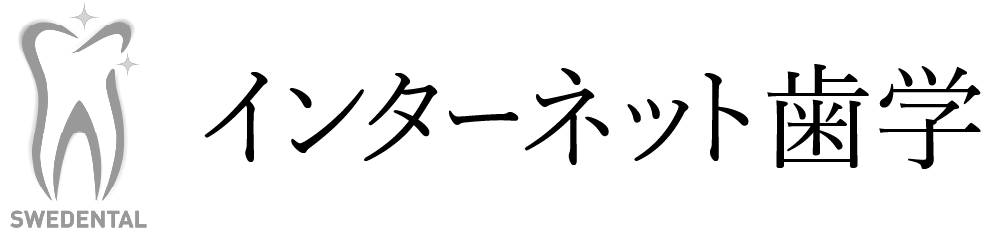バックグラウンド
垂直ラムス骨切り術は、垂直方向の逸脱(開咬)を伴わないクラス3の咬傷(下顎の予後)の治療のための顎矯正手術技術です。この技術は、1929年にLindberg et al [1]によって最初に追加の経口アプローチとして説明され、その後1954年にCadwell&Lettermanによって説明されました[2]。元の技術には、目に見える口腔外瘢痕、顎関節頭の位置異常、IMF(顎間固定)の必要性など、いくつかの欠点がありました。手術後6〜8週間の下顎と上顎の固定。したがって、この技術は徐々に変更され、Moose 1964 [3]は口腔内入口を説明し、したがって患者は顎の角度の下で目に見える術後瘢痕を取り除きました。骨切り術は現在、その指定を口腔内垂直骨切り術(IVRO)に変更しています。 Hall&McKenna 1987 [4]は、筋骨格系の変化を介してこの技術をさらに発展させ、内側翼突筋の一部を残しました。内側翼突筋は、カプート部分から切り離されていない場合、骨切り術後のカプートの位置異常を減らすことができます。実行されました。顎間固定はまだ残っていますが、今日では短く、通常4週間後に除去されます。
大まかに言えば、ずれた下顎骨を動かすために異常手術で使用される2つの既知の骨切り術があります。 IVROは、矢状分割骨切り術(SSO)とは異なり、下顎の後方移動にのみ使用できます。これは、骨切り術の設計と最終的にはそれらを安定させる方法に依存します。 IVRONの骨切り術の位置は、一般に骨接合術(チタンプレート)による固定を許可しませんが、骨切り術は顎間固定によって固定されます。これは、ジアスターゼ(筋肉の分裂)が発生し、セグメント間の安定化の可能性がない場合、下顎を前方向に動かすためにIVROを使用できないことを意味します。これはまた、下顎の子孫と組み合わせて前頭開…