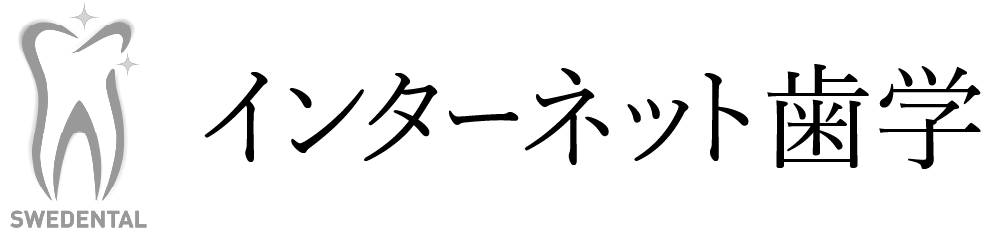クリニックでの食事分析と栄養カウンセリング
背景
食生活は虫歯の発症に中心的な役割を果たしており、多くの人にとって侵食による損傷の原因にもなります。虫歯の場合、発酵性炭水化物の細菌分解が起こり、乳酸や酢酸などの弱い有機酸が形成され、口腔環境に影響を及ぼし、歯の硬組織の脱灰を引き起こす可能性があります。侵食による損傷に関しては、もともと pH 値が低い酸性の飲み物や食べ物を摂取すると、歯の表面が摩耗する可能性があります。どちらの病気も、発症するには長期間にわたり、一定の頻度で摂取することが必要です。
酸の摂取が侵食損傷に重要であることは20世紀後半に知られるようになったが、虫歯の発症に対する食事、特に砂糖の重要性は、いわゆるヴィペホルム研究の結果が発表されて以来知られている。 1950年代に出版されました。その結果、歯科医療の分野では虫歯のリスクを減らすためのさまざまな食事に関する推奨事項が策定されました。当初は、摂取頻度を低く抑えることに重点が置かれ、1 日 5 回の摂取、つまり主食 3 回と間食 2 回が推奨されていました。 「サタデー・キャンディ」というコンセプトも、子供たちに毎日ではなく週に一度だけキャンディを食べるように教えることを目的として、早くから導入されました。多くの点で、スウェーデンは虫歯のリスクを減らすための食事に関する推奨事項の先駆者でした。
最終的に、通常の砂糖の甘味を、虫歯の原因となる細菌によって全く分解されないか、または分解される量がはるかに少ない物質に置き換えることを目的として、さまざまな甘味料が導入されました。市場に早くから導入されたものの中には、例えば、糖アルコールのソルビトールやキシリトール、アスパルテームやサッカリンなどのさまざまな人工甘味料があります。今日では、エネルギーを与えない物質とエネルギーを与えない物質に分類される物質は多岐にわたります。虫歯のリスクを減らすことを目的として食事…